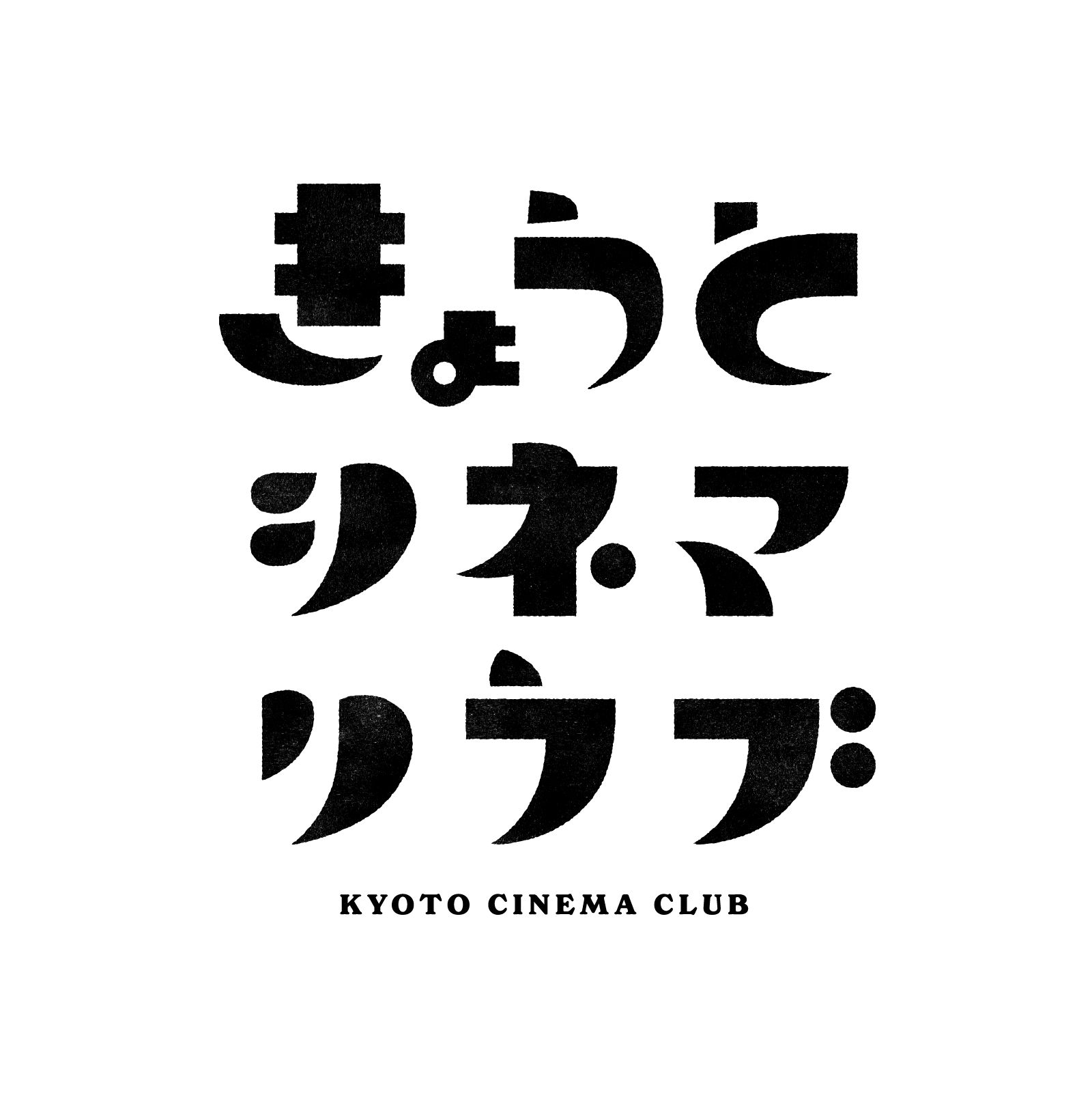Movie Review映画批評
『青春がいっぱい』The Trouble with Angels
監督:アイダ・ルピノ

『青春がいっぱい』。邦題の通りこのフィルムはたくさんの出来事で満ちている。映画は全寮制修道院女子校に入学したメアリーとレイチェルというふたりの少女と、厳しい修道院長の関係を中心に置いているものの、ひとつのゴールに向かって物語が進んでいくというよりも、3年間で彼女たちが繰り広げるハプニングの数々が短いエピソードとして詰め込まれており、そのひとつひとつを見ているだけで愉しい。
たとえば入学直前に電車で出会ったメアリーとレイチェルは、ふざけた自己紹介をした流れそのままにさらに悪ノリし、合流した他の新入生も巻き込みながら、自分たちの名前を偽って入学しようとする。メアリーはキム・ノヴァク。レイチェルはフラ・ダ・リ。もちろんすぐにバレ、校舎に着いて早々、院長に目をつけられてしまう。この場面の顛末があっさりとした印象を与えるのは、院長がふたりを説教しようと自室のテーブルの前に座らせた途端に、ショットが院長の部屋から転じ、何人かの修道女たちがロビーを往来する様子を滑らかな移動撮影で捉えるからである。そこで働く人々の姿が見えてくるのと同時に校舎のロビーが映画の舞台として立ち上がっていく。画面奥の廊下からこちらにやってくる修道女を左から右へのパンで追い、廊下と逆位置にあるマリア像の下のデスクに着くまでを映してから、ショットが切り替わると、彼女が通り過ぎたばかりのロビー右手にあるひときわ大きな扉からメアリーとレイチェルがイラついた様子で出てくる。すなわち、ふたりが院長に説教されているところをだらだらと見せず、代わりにその時間をこれから彼女たちが関わることになる人々や場所の紹介にあてているのだ。それからもメアリーとレイチェルは懲りずに悪戯を続け、院長に何度も叱られるのだが、じつのところ面と向かって説教される場面はほとんど見せられず、悪戯がバレてからすぐに彼女たちが罰として皿洗いをさせられている場面に飛ばされる。そうした説教の場面の省略が『青春がいっぱい』の各エピソードにオチと小気味よいテンポを与えており、本当ならもっと抑圧的に感じられてもいい修道院学校の雰囲気を慎重に和らげてもいる。
複数のエピソードを緩やかに繋ぎ止めるメアリー、レイチェルと院長の関係性の変化が、一方の意志にどちらかが従ったり、妥協したりすることを通して見えてこないのは、説教を省略するこのフィルムの語りによるところもあるのだろう。反発し合っていた彼女たち、主にメアリーと院長は互いに理解を深めていくのだが、それは喧嘩をすることによってでも、近くで過ごすことによってでもない。そうではなくてその人が独りでいるところを離れた場所から見つめることによって、自分の前にいるときには見せない彼女の姿を発見していくのだ。一年目の冬、寮の大部屋。メアリーは他の少女たちで騒がしいその空間から抜け出るように、窓の方へ吸い寄せられていく。窓の外を覗くと、庭には院長が独りでいる。その瞳を潤ませ、顔にはこれまでに見たことがない切なげな表現を浮かべている。院長の方も視線を察するのだが、一瞬気に留めるだけでメアリーの視野からすぐに逃れていく。外を見つめたままのメアリーは顔を徐々に上げ、空から雪が落ちてきていることに気づき、院長への注意を遮られる。嬉しそうに雪のことをレイチェルたちに伝えるが、院長がいたことは誰にもいわない。独りの院長をメアリーが見つめるとき、彼女もまた独りなのだ。以後にも何度か訪れる、このふたりだけの視線のやりとりによって、メアリーは院長への印象をあらためていく。
院長も変わる。しかし、それは根本的な人間性の変化が訪れるのではなく、修道院を統率し、ただ厳格なだけに思えた彼女の新たな側面が徐々に明らかになることで、登場人物として深みが増し、変わって見えるのだ。ある夜、院長は不器用なレイチェルがドレスづくりに失敗しているのを見て、手伝わずにはいられず、いつのまにか徹夜までしてしまう。時間を忘れて夢中になっている院長は子供のようだ。子供じみた顔をふと覗かせる大人の女性を演じるのなら、なるほどロザリンド・ラッセルがふさわしい。翌朝やってきたメアリーに対して、院長は信仰に目覚めた経緯を語ることになる。かつてはパリに住んでおり、デザイナーを目指していたが、その最中に「よりよいもの(something better)」に出会ったのだと。そこで院長がメアリーと同じように孤児であったこと、マドレーヌ・ルーシュという名前であったことがさらりと明かされる。マドレーヌが過去について話すとき、やはりメアリーは独りでそれを聞いている。この時点で映画はすでに終盤に差し掛かっており、メアリーとレイチェルは卒業を目の前にしている。
レイチェルとメアリーはつねに一緒に青春を送っていたように見えるが、このフィルムは彼女たちがともにいなかった僅かな時間を多くのハプニングの傍らで丁寧に捉えており、それによって浮かび上がる各々の孤独も『青春がいっぱい』の魅力的な側面にほかならない。だからこそ、メアリーが密かに重大な決断を下したことや、卒業直前までそれをレイチェルにさえ告げられなかったこと、あるいはレイチェルがメアリーの決断をすぐには受け入れられないことに、見る者はとくに驚くこともなく納得することができる。一見散らばったエピソードを、なにかひとつの目標に向かって奉仕させることなしにそれぞれ輝かせ、しかしその中で蓄積されていくものをささやかに掬いとる見事な手並みも、じつは50本近くのテレビドラマを職人的に撮っていたアイダ・ルピノ監督の一面としてこれから注目されていくべきだろう。
執筆者/梅本健司
「早稲田大学大学院文学研究科演劇映像学コース在籍。 NOBODY編集部。webサイト(https://www.nobodymag.com/)や2ヶ月に一度発行しているZINE「MUG」に映画評を寄稿。共著に『レオス・カラックス 映画を彷徨うひと』(フィルムアート社)、『青山真治クロニクルズ』(リトルモア)、『サッシャ・ギトリ 都市・演劇・映画 (増補新版)』(ソリレス書店)など。」