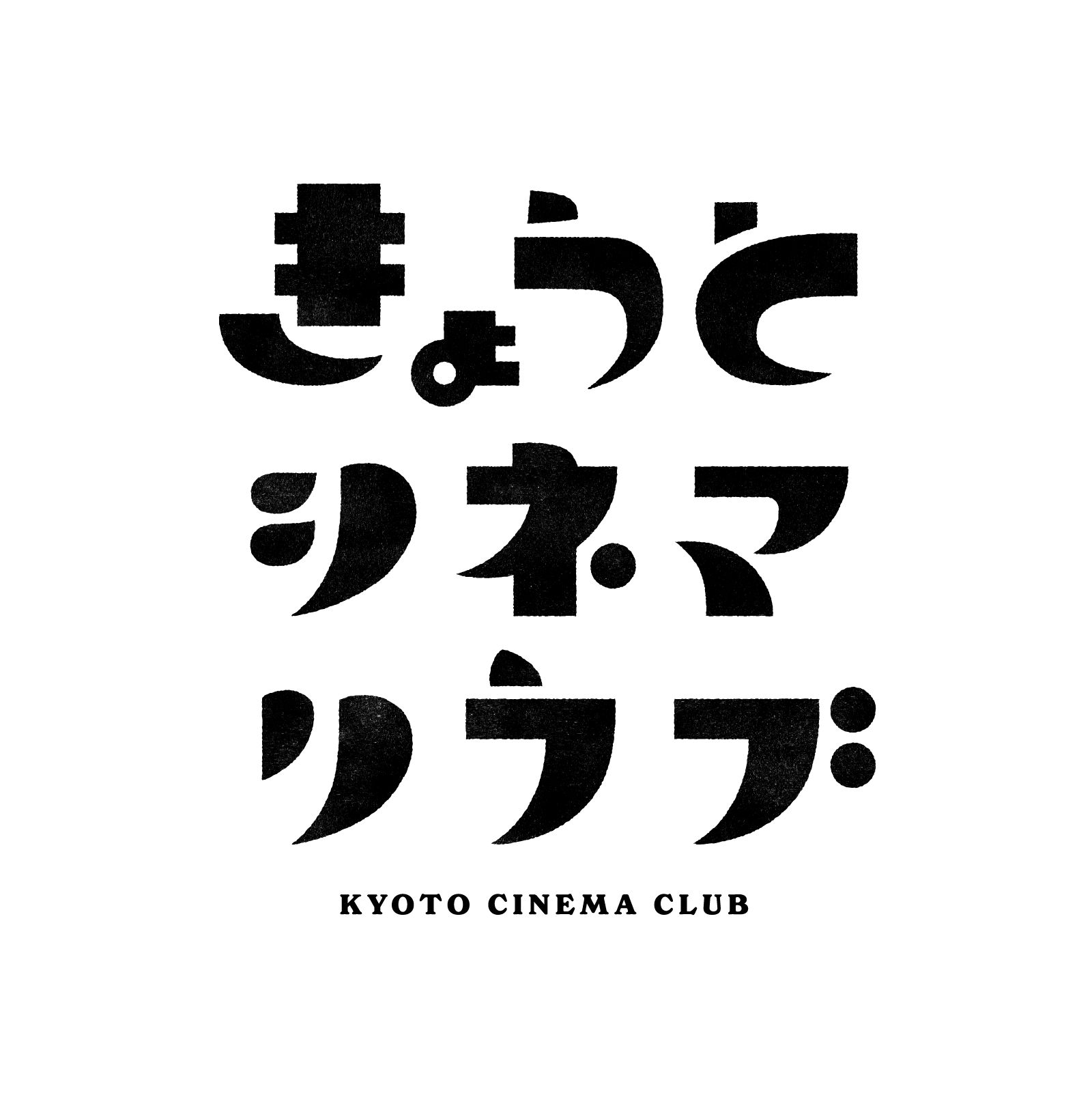Movie Review映画批評
『ラブレス』Loveless
監督:キャスリン・ビグロー/モンティ・モンゴメリー

冒頭、バイクのステップがクロースアップで映しだされ、画面右から黒いエンジニアブーツがフレームインし、ステップの前で歩みを止める。ゆっくりと後退しつつクレーンアップするカメラは、ぴったりとした黒革のスキニーパンツ、ジッパーが締められた革ジャン、男の顔を順にとらえていく。男はバイクに浅く腰掛けながら、七三分けオールバックの髪をコームで撫でつけている。コームをポケットにしまい、革ジャンのベルトをキツく締め直すと、男はバイクに跨りなおし、ゆっくりとした動作で黒い手袋とサングラスを身につける。長回しのカメラは、この間も後退しながらゆるやかに上昇しつづけているが、エンジンをかけるためにキックペダルを踏み込む男の、斜め上からのフルショットに至って一時停止する。ヘッドライトをつけ、バイクが走行を始めると、カメラもまた動きを再開する。バイクをフォローするカメラが左へとパンをすると、画面を左右に横切る車道が映される。バイクが右折をして車道に出ると、カメラも右へとパンをするのだが、速度を上げるバイクはカメラを引き離し、画面右奥へと走り去っていく。
ゆっくりとしたリズムを基礎づける二分間の長回しから開始される『ラブレス』(1984)は、キャスリン・ビグローとモンティ・モンゴメリーの共同監督による長編第一作である。物語は、バイカーのヴァンス(ウィレム・デフォー)が、レースのためにデイトナへと向かう途中、偶然通りがかった田舎町に立ち寄ることで展開される一日の出来事であるが、その主題は構築されるものとしての「男性」と、彼らによって暴力を被る存在、とりわけ彼らが外部へと排除する「女性」たちへと向けられている。革ジャンに革のパンツ、オールバックというバイカースタイルで身を固めたヴァンスの身体動作は、それらのひとつひとつをフェティッシュに、かつ批判的にとらえることを可能にするような長回しのカメラに同調するようにゆっくりと行われる。
それは、道端で立ち往生する車のパンクを強引に修理するシーンにおいてもまた示される。ヴァンスはパンクを修理しながら、革ジャンを脱いだタンクトップ姿の上半身を、車の持ち主の女性に見せつけるように動作させる。ここでヴァンスの肉体はフェティッシュに映しだされているのだが、こうした彼の「男らしい」ふるまいは、理想化されたものであるよりもむしろ、誇張されたものとしてあらわれ、それによって「男性性」のパフォーマンス性をわれわれに示す。パンク修理を終えたヴァンスが、この女性に性暴力を働き、彼女の財布から代金を奪い取るとき、「女性」を外部として排除しつつ、「男性」としてふるまおうとするヴァンスのパフォーマティヴなありようが理解され、そのようなイメージは、暴力によって支配/被支配という権力関係を強化する支配的な「男性」像をさらけ出す。
『ラブレス』は、「男らしさ」を誇張したかたちで描くことによってその構築性を暴くだけではなく、暴力を被る女性たちの抵抗する姿やその声を映しだすことによって、ステレオタイプの撹乱を企図してもいる。「男性」たるヴァンスは、彼女たちを救いだしたりはしない。ヴァンスはあくまで、彼女たちの声を聞きとる存在としてあるだけなのだ。
バイクを修理するため、仲間たちとガレージでたむろするヴァンスは、ガレージ横のガソリンスタンドでテレナ(マリン・カンター)という女性に出会い、二人は彼女のオープンカーでドライブをするのだが、彼女はドライブ中、額の傷が父によって受けたものであることや、母が父によって自殺に追いやられたことを打ち明ける。その後、テレナとヴァンスはモーテルで抱き合うのだが、発砲しながら突然部屋へと押し入るテレナの父(J・ドン・ファーガソン)は、裸のままの彼女を強引に連れ出していく。抵抗するテレナは父に対し、「彼がしたのはパパが私に何度もしたことよ」と言い返すのだが、ここでヴァンスは、彼女が父によって日常的に性暴力を受けていることを知るのである。
ヴァンスが途中で立ち寄るダイナーでウエイトレスとして働くオーガスタ(リズ・ガンズ)は、夫に先立たれて五年が経ってもなおこの町でくすぶり続けていることをヴァンスに語る。終盤のバーのシーンにおいて、彼女は思い立ってその場にいた男たちの前でストリップを披露し、嘲笑されることになるのだが、そうした彼女の姿は、ヴァンスの心のうちに、父に抵抗するテレナの声をフラッシュバックさせ、その声は、彼に自身の行為の暴力性を自覚させるものとして響いていく。抑圧に抵抗する彼女たちの姿は、ヴァンスの心のうちに自己批判的なまなざしを介入させる。『ラブレス』において物語を駆動させるのは、主人公のヴァンスではなく、つねに彼の周囲に存在する女性たちなのである。
身体の表面をぴったりと覆うバイカースタイルのファッションは、それによって自己の境界を維持しようとするものに思われるが、アルコールを摂取し、バイクを猛スピードで走らせ、ナイフ投げをし、身体に刻まれた傷を見せあいながら、お互いの男性性を確かめあうヴァンスや彼の仲間たちのマゾヒスティックな行動は、みずからの身体を死へと接近させてゆくものでもある。それらは「男性」をかたちづくることを超えて、むしろ自分を自分で殺すことへと結びつくものであるだろう。「行き着く先はどうせ地獄だ」あるいは「行き先なんてない/走るだけだ」というヴァンスの台詞において示されるように、彼らはそうした自己に対する暴力について自覚的でもある。あらゆるものを排除しながら自己画定してゆくその運動は、ついに自分自身をも排除するに至る。「女性」を外部として切り分けることで自らを主体化する「男性」の暴力的な排除の論理は、加速していくことでいつしか「男性」自身の身体さえ排除しうるものとなっていくのである。
それは、田舎町で暮らす「普通の」人々が、バイカーたちを「犬」に喩えて見下すこと、とりわけテレナの父がバイカーたちを「ウズラ」とみなし、殺しても問題はない存在として、ついには殺害を画策しようとすることにおいても反復されている。『ラブレス』は、テレナの抵抗によって悲惨な終わりを迎えるが、恣意的で暴力的なカテゴリーを維持しつづけようとすることが、あらゆる存在に対して悲劇的で残酷な結果をもたらしうるということを、映画はわれわれに示すだろう。
執筆者/板井仁
宮城県出身。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程。専攻は映画研究。論文に「諏訪敦彦の映画制作 『ライオンは今夜死ぬ』(2017)を中心として」。その他、IndieTokyoやNobody、neoneo webに寄稿。