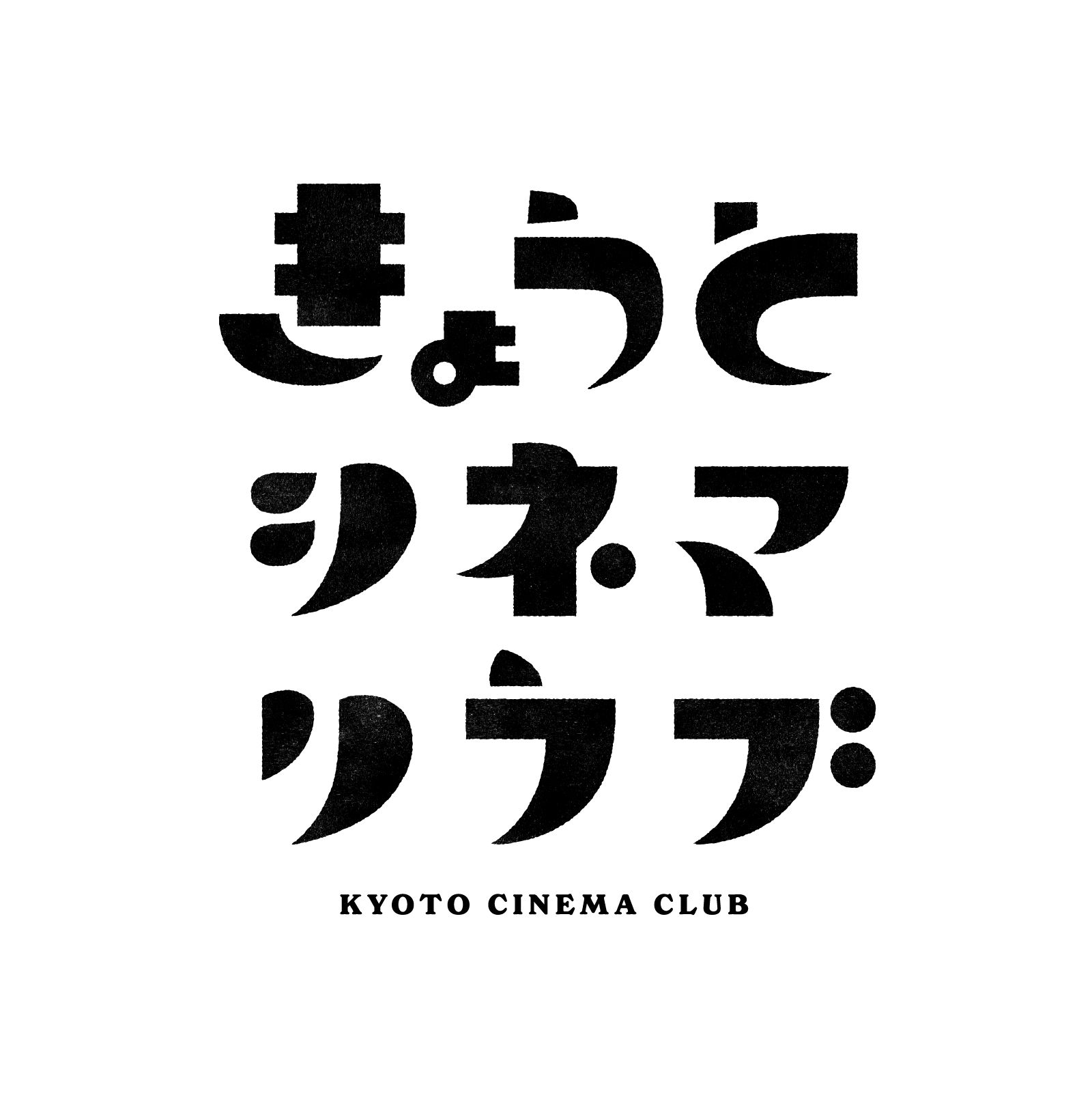Movie Review映画批評
『天使の復讐』Ms.45
監督:アベル・フェラーラ

2019年に放送がスタートしたA24製作のHBOドラマ『ユーフォリア/EUPHORIA』に、学校では冴えない日々を送るキャットというぽっちゃり体型の人物が登場する。彼女はあることをきっかけに、自分自身の身体を男たちの性的なまなざしの前に差し出し、彼らの欲望に主体的に関わっていこうとするキャラクターだ。シーズン1の第6話、キャットはハロウィンパーティーに派手なメイクの修道女姿であらわれると、こう言って友人を戸惑わせる。
「『天使の復讐』のサナだよ。見た方がいい」
『ユーフォリア/EUPHORIA』はアメリカのZ世代の若者を描いたドラマだが、キャットは悶々としていた時期にきっとカルトな映画を見まくっていたのだろう。わかる人にはわかる、ちょっと笑えるシーンだ。しかし『ユーフォリア/EUPHORIA』が性的依存や薬物依存の問題を中心の主題にしたドラマであることへ目を向ければ、必然的にアベル・フェラーラ作品が召喚されたのだと思えなくもない。フェラーラの映画には常に人間の欲望や、それに伴う虚飾の影がつきまとっている。
1981年にアメリカで公開された『天使の復讐』は、いわゆるレイプ・リベンジ・エクスプロイテーションと呼べるだろう。しかし本作はエクスプロイテーション映画であることを超えて、人間という生き物の不可解さに触れていくような深みに満たされた作品でもある。
主人公のサナ(ゾーイ・タマリス)はアパレル企業に勤めるアシスタント。彼女は口をきくことができないのだが、そればかりか他人と比べてどこか調子がワンテンポずれているような節があり、いつも無表情でいる。モスグリーンの瞳は常に遠くに焦点が注がれていて、まるで真っ暗な海をさまよう深海魚の目のようだ。
ある日、暴漢に性的暴行を受け、犯人をアイロンで殴り殺してしまったことをきっかけに、彼女の日常には徐々にヒビが入りはじめる。サナは暴行を受けたこと、犯人を殺してしまったことを隠し、いつもと変わらず出勤する日々を続けようとするのだが、会社では服飾デザイナーの男性上司がいつものように「Vネックと言ったろ! 誰がスクープネックと言った!?」などと怒鳴り声をあげている。サナはそれまで受け流せていた彼の怒鳴り声に身がすくんでしまう。嫌味ったらしいその上司は「ハンディキャップがあるのはわかるが、普通の人より努力するんだ」とサナをなじるのだが、それでも彼女は誰かに助けを求めることはせず、感情のとぼしい表情でそこにいることしかできない。
きっとサナには怒り方も泣き方もわからないのだ。怒ること、泣くことは、それによって他者の反応が引き出せることを期待している人間の情動だ。彼女はそのような機会を得られず、孤立し、誰の助けも借りられない状況で、「普通の人」のふりをして懸命に生きて来た人物のように思える。しかし暴行事件をきっかけに、サナはこれまで出来ていた「普通の人」のふりが出来なくなってゆく。ついにサナは、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の『欲望』(1967)でデヴィッド・ヘミングスがモデルを撮影していたのによく似たスタジオで、「僕は美に夢中なんだ」と言い寄ってきた写真家の男を、暴漢から奪った45口径のピストルで撃ち殺す(本作の原題は”Ms. 45”だ)のだ。そのときのサナの表情に、もうこれまでの戸惑いの影はない。それは、「美しい」がために、これまで獲物を狩るような男たちのまなざしに踏み躙られてきた彼女が、ピストルの一撃によって初めて彼らを見つめ返した瞬間だ。
この世の男という男を殺す決意をしたサナは、真っ赤なリップを塗る。赤色が散りばめられた本作で、サナに撃たれた男たちの体から吹き出す血はどちらかというとジャン=リュック・ゴダールやハーシェル・ゴードン・ルイスの映画の中の血のようなまがい物のペンキ色の赤だが、彼女のリップの方こそが何よりも血の色をしている。チークは頬の中心からもみあげの上あたりまで斜めに引かれ、真っ黒なアイラインとマスカラが楕円型の瞳を縁取る。これまでのシーンでの、部屋の調度品のひとつひとつ、羽織る毛布、黒いベレー帽と真っ赤なシャツの組み合わせといった何もかもが可愛らしかった彼女とは対照的に、ここでのメイキャップと衣装は冷たい表情でランウェイを闊歩するモデルのようだ。彼女の「感情の乏しい表情」が、メイキャップと衣装によって「モデルのような冷たい美しさ」に変換される。サナは自分自身の使い方をついに発見したのだ。
胸元が大きく開いたVネックの服を身につけ、胸の谷間を誇示するサナ。前述した上司の「Vネックと言ったろ!」という叫びを思い出すならば、彼女はここで、男性目線の「女らしさ」を自ら引き受けることによって復讐を遂行しようとしている。そこには「ハニートラップ」の主体となれるという有用性だけでなく、一度は男たちに貶められた自尊心を彼らの欲望のなかにある「女らしさ」をあえて引き受けることで取り戻そうという、複雑な意識の運動がある。
やがて、「普通の人」のふりをやめて本当の自分を見出したサナに2度目の決壊が訪れることとなるだろう。彼女は酒場で知り合った男に、別れた妻との性的な体験や妻への支配欲に満ちた話を、罠を張る狩人のようなまなざしで聞いているのだが、男は徐々に、妻が他の女性と関係を持っていたことや、それに絶望して飼い猫を絞め殺したことまでを話しだし、ついにはサナの目の前で自ら命をたってしまう。この瞬間、サナは他者の奥底を覗こうとしすぎたあまり、人間とはその表面だけを見て一方的に裁けるような単純さに収まる存在ではないという事実に触れてしまう。
クライマックスとなるハロウィンパーティーで、修道女姿のサナは仮装した男たちを次々と撃ち殺してゆくのだが、花嫁の仮装をした男を撃ち殺したとき、彼女はちょうど下腹部にナイフを構えた女に背後から突き殺されることとなる。イメージとしての「女」として男たちに尊厳を蹂躙され、だからこそイメージとしての「女」を引き受け、イメージとしての「男」を殺してきた彼女は、ついに花嫁衣装の男や、ペニスのようにナイフを突き立てた女といった、「イメージ」の渦の中に落ち窪んでゆき、あらゆる境界が不分明になった末、この世界から滅却されてしまう。この身も蓋もない即物性は、その後のフェラーラ作品にも見て取れる特徴で、『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』(1992)のキリストがいかなる神秘性も帯びずにその姿をあらわすシーンなどに顕著だ。
『天使の復讐』でサナを演じたゾー・ルンド(旧名ゾー・タマリス)は、1997年に薬物中毒により37歳でその生涯を閉じることとなる。彼女は時に熱心にキリストへの思慕を語り、時にヘロインの合法化を提唱していたそうだ。フェラーラのその後のフィルムは性的依存に加え、薬物依存、そしてキリストという主題が延々と繰り返されることとなる。そこに恐らくは、イタリア−アイルランド系移民の子でありカトリック教徒として育てられたフェラーラ自身の出自とともに、彼女の死も深く影を落としているだろう。『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』ではハーヴェイ・カイテルが、車上の女たちに性的な身振りを行わせ、自らは自慰行為をするだけで彼女たちに触れることはないという悪名高いシーンがあり、それはイメージとしての欲望しか持てない人間の性質を描いている。『アディクション』(1995)はタイトルそのものからして「依存」という主題を指しているし、『4:44 地球最期の日』(2011)では、気候変動による避けがたい地球滅亡という設定を借りながら、もはやすべての欲望に意味が失われたあとの虚無感がさらけ出されてすらいる。
ゾー・ルンド亡き後も、アベル・フェラーラは映画を撮り、国際映画祭を飛び回り、酒を飲み、恐らくはドラッグも欠かさず摂取しているのだろうか。ミュージシャンでもある彼は72歳となった今も、ステージに上がってギターをかき鳴らし叫んでいる。『天使の復讐』のラストシーン、虚飾を纏うことで生き抜こうとしたサナを偲び涙を流す老女の派手な首飾りや真っ赤なリップをつけた美しい横顔に、ギターを抱え一心不乱に歌う現在のアベル・フェラーラその人の面影が重なって見える。
執筆者/鈴木史(映画監督・美術家・文筆家)
映画美学校修了後、東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻監督領域修了。映画と現代アートのフィールドを横断しながら活動するとともに、カルチャー批評誌「NOBODY」ほかで映画評を執筆。上映会でのトークも行う。 映画『祈ることは思考すること』(2022/監督・編集)、個展「Miss Arkadin」(2022/塩竈市杉村惇美術館)、連載「一本の(映画・映像・動画......)から考える○○のこと」(せんだいメディアテーク)など。